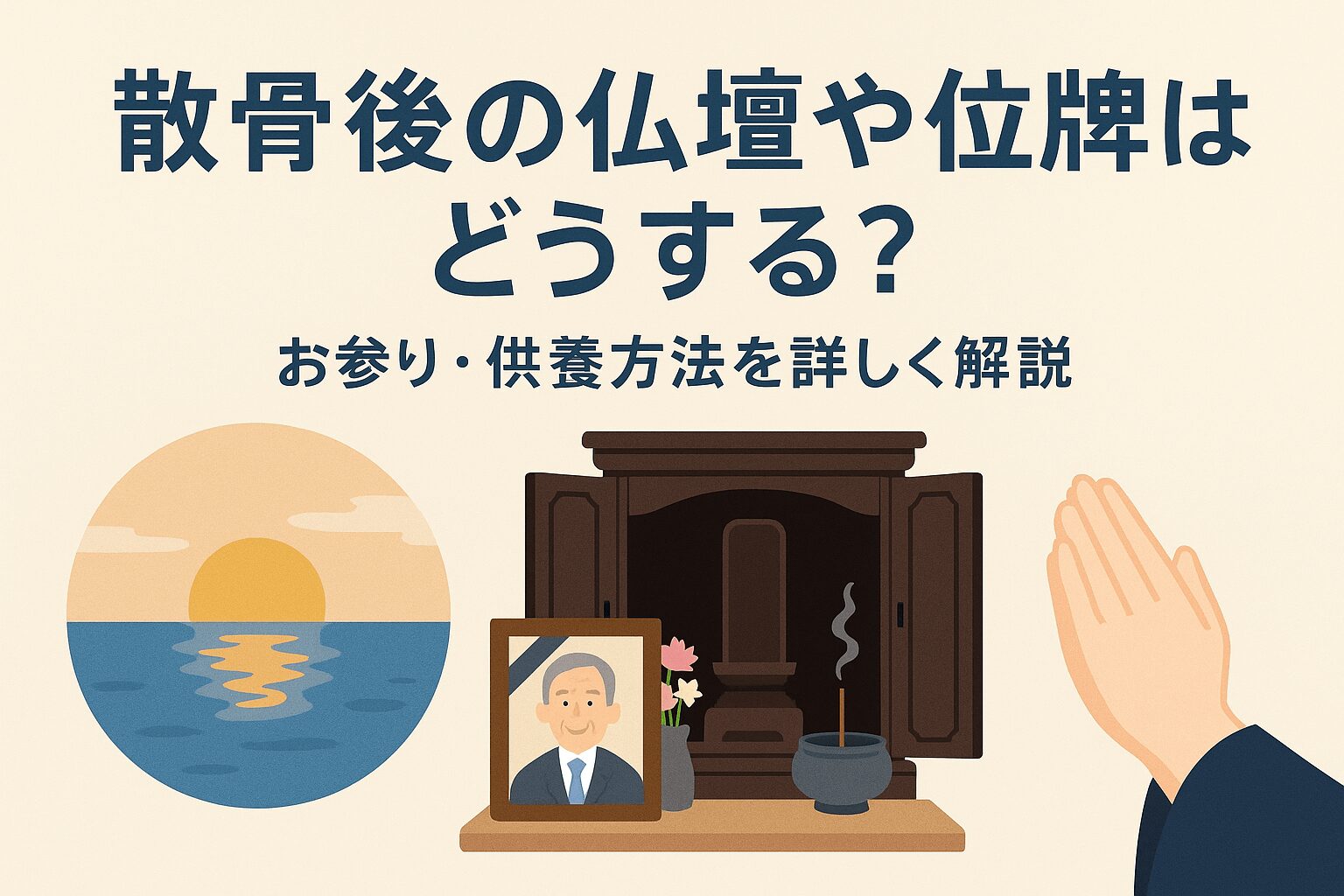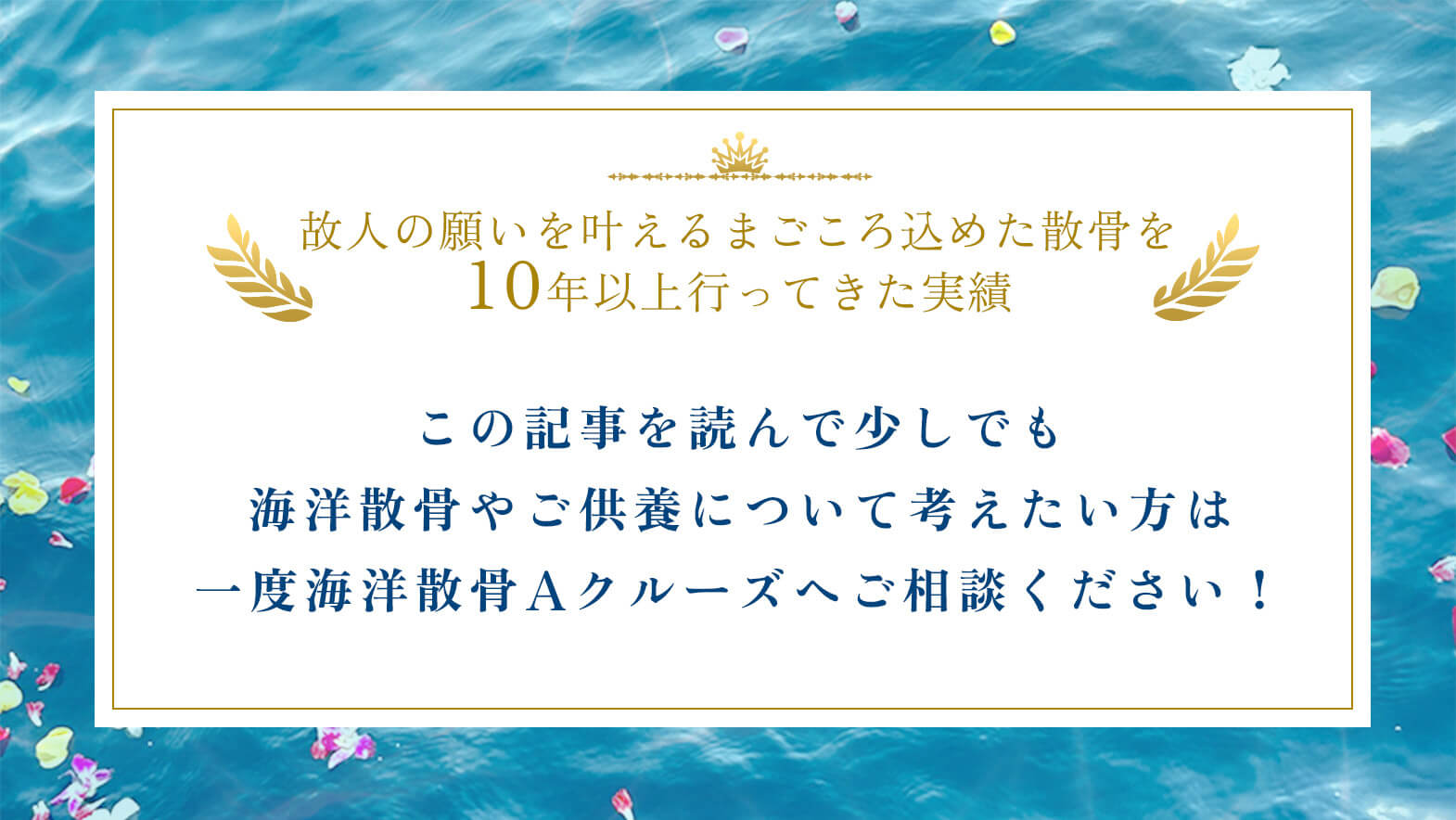「散骨したら、仏壇や位牌は必要ないの?」
「故人を自然に還したいけれど、手をあわせる場所がなくなってしまうのは寂しい」
大事な方を亡くし、散骨を考えるなかで、その後の供養方法について悩む方も多いのではないでしょうか。
本記事では、散骨後の位牌の必要性や既に位牌がある場合の処分方法、散骨した後の具体的な供養方法について詳しく解説します。
あなたの気持ちに寄り添った供養の方法を見つけ、心の整理をしていきましょう。
Contents
位牌と仏壇の概要
散骨を考える上で、まずは位牌と仏壇が本来どのような意味を持つのかを知っておくことが重要です。
- そもそも位牌とは?
- 位牌を安置する仏壇とは?
- 位牌が必要ない宗教
そもそも位牌とは?
位牌とは、遺族が供養するための対象となる木製の札を指しており、故人の魂が宿る場所とされています。
葬儀の際には「白木位牌」が用いられ、四十九日の法要で僧侶にお経をあげてもらい、白木位牌から本位牌へと故人の魂を移す「開眼供養」を実施します。
本位牌は、お寺が用意するものではなく、家族が仏具店などで手配するのが基本です。
本位牌の大きさやデザインはさまざまで、仏壇の大きさにあわせて選ぶことが多いとされています。
ただし、仏教のなかでも宗派によって位牌に対する考え方は異なるため注意が必要です。
自身の宗派での正式な方法がわからない場合は、菩提寺に相談するとよいでしょう。
位牌を安置する仏壇とは?
仏壇は、故人や先祖を祀る場所と思われがちですが、本来は家の中に設置する「小さなお寺」であり、ご本尊を祀るためのものです。
仏教では、亡くなった方は仏様になると考えられています。
仏様になった故人や先祖の位牌をご本尊と一緒に仏壇に安置し、日々手をあわせることは、ご本尊にお参りすることと同じ意味を持ちます。
かつて仏壇は多くの家庭で日常生活に溶け込み、家族の心のよりどころとして大事にされてきました。
現代では核家族化やマンション暮らしなどの住宅事情により、伝統的な大きな仏壇を持たない家庭も増えています。
しかし、お盆やお彼岸に実家で仏壇に手をあわせる行為は、小さなお寺が家族にとって今も大事な場所であることの表れといえるでしょう。
位牌が必要ない宗教
仏式の葬儀では位牌を用意することが一般的ですが、宗派によっては位牌を必要としない場合があります。
多くの仏教宗派は、亡くなった方は仏の弟子となり、成仏するために修行するといった考え方です。
そのため、故人が無事に成仏できるよう、遺族が祈りを捧げる対象として位牌を用います。
しかし、浄土真宗の考え方は「人は亡くなるとすぐに、ご本尊の導きによって極楽浄土に往生し、仏になる」というものです。
信仰を決定した時点で誰もが仏になれることが約束されていると考えるため、他の宗派のように故人の魂を位牌に宿らせて成仏を祈る必要がないのです。
そのため、浄土真宗では一部の地域や考え方を除き、基本的に本位牌は使用しません。
散骨する場合の位牌の必要性

散骨をするからといって位牌や仏壇を用意しなければならない、あるいは処分しなければならない決まりはありません。
散骨を実施するタイミングとして、四十九日法要を区切りにする方もいれば、一周忌や三年忌など、ご遺族の気持ちの整理がついてから行う方もいます。
もし葬儀で白木位牌を用意し、四十九日までに本位牌を作った場合、散骨の際に位牌をどうするかは自由です。
故人と一緒に最後のお別れをしたい気持ちがあれば、散骨場所まで丁寧に包んで持参する方もいます。
もちろん、自宅に置いていっても大丈夫です。
また、無宗教の葬儀などで、そもそも位牌を作っていない場合は散骨のためにあえて新しく作る必要はありません。
遺骨をすべて散骨してしまうと、手をあわせる対象がなくなってしまうと感じる方もいます。
その場合は、心の拠り所として自宅に位牌を作り、小さな仏壇を置いて供養するのも1つの選択です。
もともと位牌があった場合の処分方法
散骨を機に、すでに自宅にある位牌を処分したい場合、適切な手順を踏む必要があります。
- 閉眼供養とお焚き上げ
- 永代供養
閉眼供養とお焚き上げ
本位牌には、四十九日法要などで「開眼供養」が行われ、故人の魂が宿っているとされています。
そのため、位牌は単なるモノとして処分できません。
処分する前には、宿っている魂を位牌から抜くための儀式である「閉眼供養」が必要です。これは「魂抜き」や「お性根抜き(おしょうねぬき)」とも呼ばれます。
閉眼供養が終わってからは、位牌はモノに戻るため、お焚き上げによる処分が可能です。
お焚き上げは、基本的には菩提寺にお願いします。
もし、お寺との付き合いがない場合は、僧侶の手配を行ってくれる業者やお焚き上げを専門に行う業者に依頼することも可能です。
永代供養
位牌の「永代供養」を受け付けているお寺もあります。
永代供養を依頼すると、お寺が責任をもって位牌を預かり、一定期間供養してくれます。
その後、最終的には閉眼供養を行い、お焚き上げまでしてもらえるため、自分の代で管理できなくなっても安心です。
散骨を選んだ後、自宅にある位牌をどうするかは、家族の供養に対する気持ち次第で変わります。
位牌がなければ供養ができないわけではないので、家族でよく話し合い、全員が納得できる方法を選びましょう。
散骨していても法要や法事はできる?

遺骨をすべて散骨して手元にない場合でも、法事や法要を実施することは可能です。
法事や法要は、本来仏教の儀式です。
しかし、現代では故人を偲び、親族が集まる大事な機会として、また遺族が気持ちの整理をつけるための節目として重要な役割を持っています。
付き合いのあるお寺があれば、一周忌や三回忌などの法要を執り行ってもらえるか相談してみるとよいでしょう。
また、特定の儀式にこだわらなくても、命日やゆかりのある日に親族で集まり、食事会を開いて故人の思い出を語り合うことも立派な供養になります。
たとえば、散骨した海が見えるレストランなどを会場に選べば、故人をより身近に感じられるかもしれません。
散骨した後の供養方法
散骨をした後、具体的にどのように故人を偲び、供養していけば良いのでしょうか。
現代のライフスタイルにあわせた、以下の方法を紹介します。
- 手元で供養する
- 遺骨の一部を墓地に納骨する
- 祭壇や仏壇を設ける
手元で供養する
1つ目は、遺骨のすべてを散骨せず、一部を「手元供養」として自宅に残す方法です。
手元供養は、お墓を持たない選択をした方や、故人をいつも身近に感じていたい方に選ばれています。
手元供養品には、パウダー状にした遺骨を納める小さな骨壺や、遺骨を納められるよう加工されたペンダントや指輪などのアクセサリーといったさまざまな種類があります。
これらを写真や季節の花と一緒に飾ったり、あるいはアクセサリーとして身に着けたりすることで、お墓の代わりとしていつでも好きなタイミングで故人に語りかけられるでしょう。
親族で遺骨を少しずつ分けあう「分骨」という形にも適しており、故人の遺志を尊重しつつ、遺された家族のそばにいたいという気持ちにも配慮できる方法です。
【合わせて読みたい記事】
遺骨の一部を墓地に納骨する
2つ目は、遺骨の一部を墓地に納骨する方法です。
親族のなかには、遺骨をすべて散骨することに抵抗を感じる方や、お墓に納めるべきだと考える方がいるかもしれません。
そうした場合は、故人の遺志を尊重して大部分は散骨しつつ、一部の遺骨をお墓に納めることで、後々のトラブルを避けられます。
菩提寺や先祖代々のお墓がある場合は、散骨を希望する旨を事前にお寺や親族へ相談するようにしましょう。
祭壇や仏壇を設ける
供養方法として、祭壇や仏壇など自宅に故人を偲ぶための場所を設ける手段もあります。
祭壇や仏壇には、故人の写真や思い出の品、お花などを飾ります。
祭壇や仏壇を準備することで、散骨したことを知らない方が訪ねて来た場合でも、故人を供養したい気持ちに応えられるでしょう。
大事なのは立派な祭壇や仏壇を用意することではなく、故人を偲び、語りかけられる空間を自身の気持ちにあわせて作ることです。
自宅で遺骨を保管する際の注意点

手元供養などで遺骨を自宅に保管すること自体は、何も問題ありませんが、遺骨を良い状態で保つためにはいくつか注意したい点があります。
まず、遺骨は湿気に弱くカビが発生しやすい性質があるため、保管場所は風通しのよい場所を選び、湿気がこもる押入れなどは避けるようにしましょう。
直射日光が当たりすぎる場所も、結露の原因になる場合があるため適していません。
また、仏壇がある場合の安置場所にも注意が必要です。
仏壇は本来、ご本尊を祀る場所であるため、遺骨そのものを仏壇の中に安置することは、宗教的な意味合いからすると適していないとされています。
遺骨は、写真や花と一緒に飾るための小さな祭壇を設けて安置するのが適切です。
まとめ
ここまで、位牌と仏壇の概要や位牌の処分方法、供養方法について解説しました。
- 散骨をしても、心の拠り所として位牌や仏壇を持つかは自由
- もともとある位牌を処分する際は、お寺による「閉眼供養」と「お焚き上げ」が必要
- 遺骨をすべて散骨していても、法事や法要、偲ぶ会を開くことは可能
- 散骨後の供養には手元供養や分骨、祭壇を設けるといったさまざまな形がある
- 遺骨を自宅で保管する場合は、湿気やカビ、安置場所に注意する
近年はさまざまな供養方法が存在していますが、何よりも大事なのは、自身や親族が納得できる形で故人を想い続けることです。
この記事で紹介した内容を参考に、あなたのライフスタイルや価値観にあった、心安らぐ供養の形を見つけてみてください。