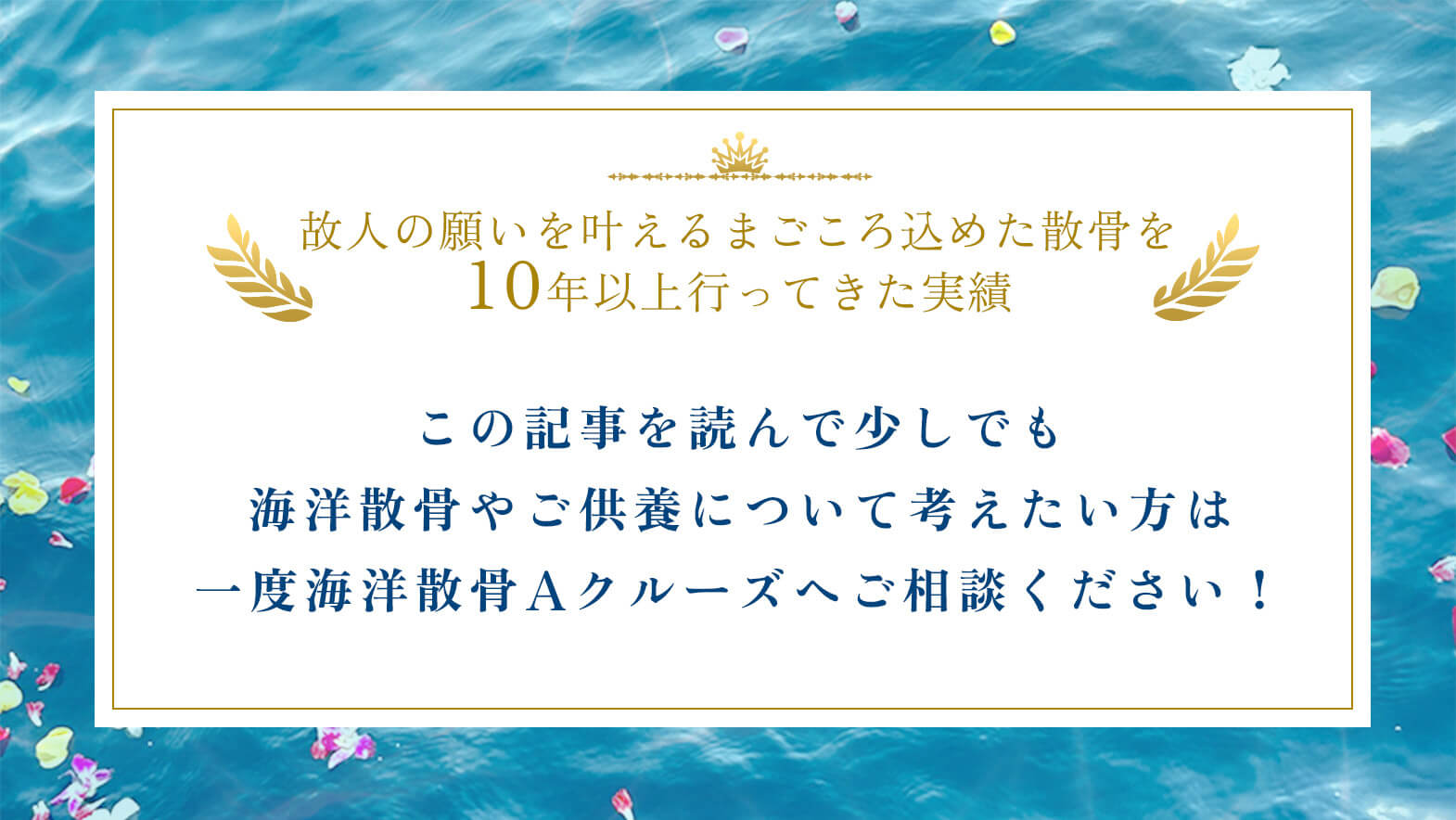遺骨を埋葬・納骨する際に必要な書類が、「埋葬許可証」です。
埋葬許可証がなければ、遺骨をお墓などに納骨することができません。
この記事では、埋葬許可証を取得する方法や再発行の手順、必要な場面について詳しくまとめました。
埋葬許可証を取得する・紛失してしまった方は、ぜひ参考にしてください。
Contents
埋葬許可証とは何か
まずは、埋葬許可証についての理解を深めましょう。埋葬許可証は次のような意味・役割を持っています。
埋葬許可証は土葬をするために必要な書類
本来埋葬許可証は、文字通り土葬の許可証を指しています。
現在の日本ではほとんどの遺体が火葬されますが、ごく一部の地域で今もなお土葬が続いているのです。
このような風習が残っている地域では、埋葬許可証を取得してから土葬をします。
納骨時にも埋葬許可証が必要
土葬が一般的でなくなった現在では、「死体火葬埋葬許可証」を略して「埋葬許可証」と呼んでいます。
死体火葬埋葬許可証は、遺体の火葬と埋葬の両方を許可する書類です。
このような理由から、「埋葬許可証」と聞いた時には、土葬用の許可証ではなく死体火葬埋葬許可証を略した書類を指すと考えて良いでしょう。
埋葬許可証の表記は自治体によって異なる
埋葬許可証は公式な文書でありながら、自治体によって多少表記が異なります。
例えば、「火葬・埋葬許可証」「死体火葬・埋葬許可交付申請書」「埋葬許可証」などの表記が存在するため、取得時は役場で書類の用途を伝えた上で適切な書類を発行しましょう。
埋葬許可証を手に入れる方法

埋葬許可証を発行する方法は、以下を参考にしてください。
大半の手続きは、親族のみでなく葬儀社も代行可能です。
- 死亡届・死亡診断書を役所に提出する
- 火葬許可申請書を役所に提出する
- 火葬許可証を火葬場に提出・埋葬許可証を受け取る
1.死亡届・死亡診断書を役所に提出する
埋葬許可証を受け取るためには、死亡届・死亡診断書(死体検案書)を故人の本籍地/死亡地または届け人の所在地の役所に提出します。
死亡届・死亡診断書は故人が海外で亡くなった場合を除き、届け人が故人の死亡の事実を知った日を1日目として7日以内に届ける必要があります。
それぞれの書類の違いは、以下を参考にしてください。
- 死亡届・死亡診断書:病院で亡くなった場合や死亡が確認された場合は病院に準備してもらえる
- 死体検案書:事故死・変死・原因不明の自宅死の場合に発行される
死亡届・死亡診断書・死亡検案書を役所に届ける作業は、葬儀社に代行してもらえます。
2.火葬許可申請書を役所に提出する
役所には死亡届・死亡診断書と同時に、火葬許可申請書も提出します。火葬許可申請書は、役所の窓口またはホームページで手に入ります。
遺体を火葬するために必要な許可証が、火葬許可証であり火葬許可申請書を提出することで手に入ります。
こちらの提出作業も、葬儀社が代行可能です。
3.火葬許可証を火葬場に提出・埋葬許可証を受け取る
火葬許可証は火葬の当日に火葬場に提出します。
火葬と骨上げの儀式が終わった後に、火葬場から埋葬許可証を受け取ってください。
埋葬許可証は骨壷と一緒に収められているケースが多いことから、直接受け取れなかった場合は骨壷を確認してみましょう。
埋葬許可証が必要な場面

埋葬許可証は次のようなシーンで必要になります。納骨が済んだ後も、埋葬許可証を紛失しないように保管してください。
埋葬許可証が必要になるのは納骨時と改葬時
火葬場で受け取った埋葬許可証は、納骨時に納骨先の管理者に提出します。
一般的には納骨は火葬後すぐではなく、四十九日法要の後に実施されるため、この期間に埋葬許可証を紛失しないように注意してください。
また、納骨が済んだ後も埋葬許可証を処分してはいけません。
なぜなら、何らかの理由で改葬が必要になった時にも、埋葬許可証を新しい納骨先に提出しなければいけないためです。
散骨の場合も埋葬許可証が必要になる可能性がある
近年人気が高まっている供養の方法に、散骨があります。
散骨では、遺骨をパウダー状にした上で、海や山に撒いて故人を供養します。
一般的には散骨時に埋葬許可証が必要であるというルールは存在しません。
しかし、埋葬許可証を必須提出書類に定めている業者も多いことから、散骨でも埋葬許可証を用意するべきだと考えておくと良いでしょう。
埋葬許可証を再発行する手順

特に埋葬から何年もの時間が経過してから改葬を決めた時には、埋葬許可証を紛失してしまう事例が多いです。
埋葬許可証を紛失してしまった場合は、以下の方法で再発行しましょう。
埋葬許可証を発行してから5年以内の場合
埋葬許可証を発行してから5年以内の再発行はスムーズに進みます。
自分の身分証明書と印鑑を用意して役所の窓口に行けば、すぐに埋葬許可証を再発行してもらえるでしょう。
埋葬許可証を発行してから5年以上経過している場合
埋葬許可証を発行してから5年以上経過している場合には、役所で埋葬許可証が破棄されている可能性があります。
そのため、5年以上経過してしまった埋葬許可証を再発行したい方は、最初に火葬場に行き火葬証明書を取得しなければいけません。
手に入れた火葬証明書を持って役所を訪れ、埋葬許可証を再発行してもらいます。
民営の火葬場を使用した場合
公営の火葬場は、「火葬の記録を30年残す」ことが義務付けられています。
しかし、民営の火葬場は独自のルールで火葬の記録を残しているため、火葬証明書の発行に手間がかかる可能性があるでしょう。火葬証明書の発行について、直接火葬場に相談してみてください。
埋葬許可証を発行するときの注意点

埋葬許可証を発行する時には、次のような注意点を意識してください。
誤った認識で埋葬許可証を扱うと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
納骨時には埋葬許可証の原本が必要
納骨の時には、埋葬許可証の原本が必要です。コピーやデータ化された埋葬許可証は利用できません。
埋葬許可証は故人が亡くなったという事実を示す重要な書類です。コピーではなく、必ず原本を正しく保管するようにしてください。
分骨時には複数の埋葬許可証が必要になる
遺骨を分けて複数のお墓に納骨する・一部を手元供養することを、分骨と呼びます。
分骨の場合は複数の納骨先があるため、分骨の数だけ埋葬許可証が必要になるのです。
火葬の段階で分骨が決まっている場合には、複数枚の埋葬許可証の発行を依頼してください。
遺骨のうちごく一部を納骨する場合でも、必ず埋葬許可証が必要です。
埋葬許可証のみを発行してもらうことはできない
埋葬許可証は火葬許可証がなければ発行してもらえません。
火葬後に火葬場で照明印をもらった書類のみが、埋葬許可証として認められます。
このような理由から埋葬許可証のみの発行は、不可能であることを知っておきましょう。
手元供養をする場合でも埋葬許可証を保管しておくべき
遺骨の全てまたは分骨後に遺骨の一部を自宅で供養することを、手元供養と呼びます。
故人を供養する方法が多様化した現在では、オブジェのような骨壷や遺骨を身につけられるネックレスも流通しています。
「手元供養であれば埋葬許可証は必要ない」と考える方もいるようですが、将来的にお墓などに納骨する・散骨する可能性を考えて、埋葬許可証を取得した上で保管しておきましょう。
海外で亡くなった時に必要な対応について
故人が海外で亡くなった場合でも、遺骨を日本に移動させて納骨するためには、死亡届や埋葬許可証が必要です。
現地の日本大使館や領事館に届け出て、必要な書類を発行してもらいましょう。
防腐処理をした上で遺体を搬送するまたは、現地で火葬を済ませてから遺骨を持ち帰る2通りの方法があり、国外で火葬を済ませた場合は帰国してから改葬許可申請後に納骨許可を得ます。
国内での手続きと比較して複雑であるため、大使館・領事館に相談しながら話を進めてください。
埋葬許可証を発行するために必要な期間と費用

埋葬許可証の発行は、通常即日その場で行われます。
そのため、埋葬許可証の発行まで何日も待たなければいけないようなことはないと考えて良いでしょう。
また、役所で受け取る火葬許可証の申請費用は自治体によって異なるものの、数百円程度です。
納骨までの流れ
最後に、火葬を終えて埋葬許可証を受け取った後の納骨までの流れについて説明します。
納骨時期には「火葬後◯日以内に納骨する」などの明確なルールがありません。
一般的には四十九日法要後に納骨を行う家庭が多いですが、親族や納骨先と相談しながら納骨時期を決定してください。
お墓に遺骨を納める場合には、石材店にも連絡して納骨のスケジュールを立てていきます。同時に文字入れの依頼も済ませると良いでしょう。
まとめ
埋葬許可証は遺骨を納骨するために欠かせない書類です。
役所で火葬許可証を受け取り、火葬時に火葬場で押印してもらうことで、埋葬許可証が手に入ります。
埋葬許可証を紛失すると、お墓・納骨堂などへの納骨が不可能になるため、よく注意してください。
また、埋葬許可証は再発行可能です。許可証をなくしてしまった時には、役所または火葬場に相談して、再度埋葬許可証を手に入れましょう。
この記事を参考に、埋葬許可証を正しく扱うことが大切です。