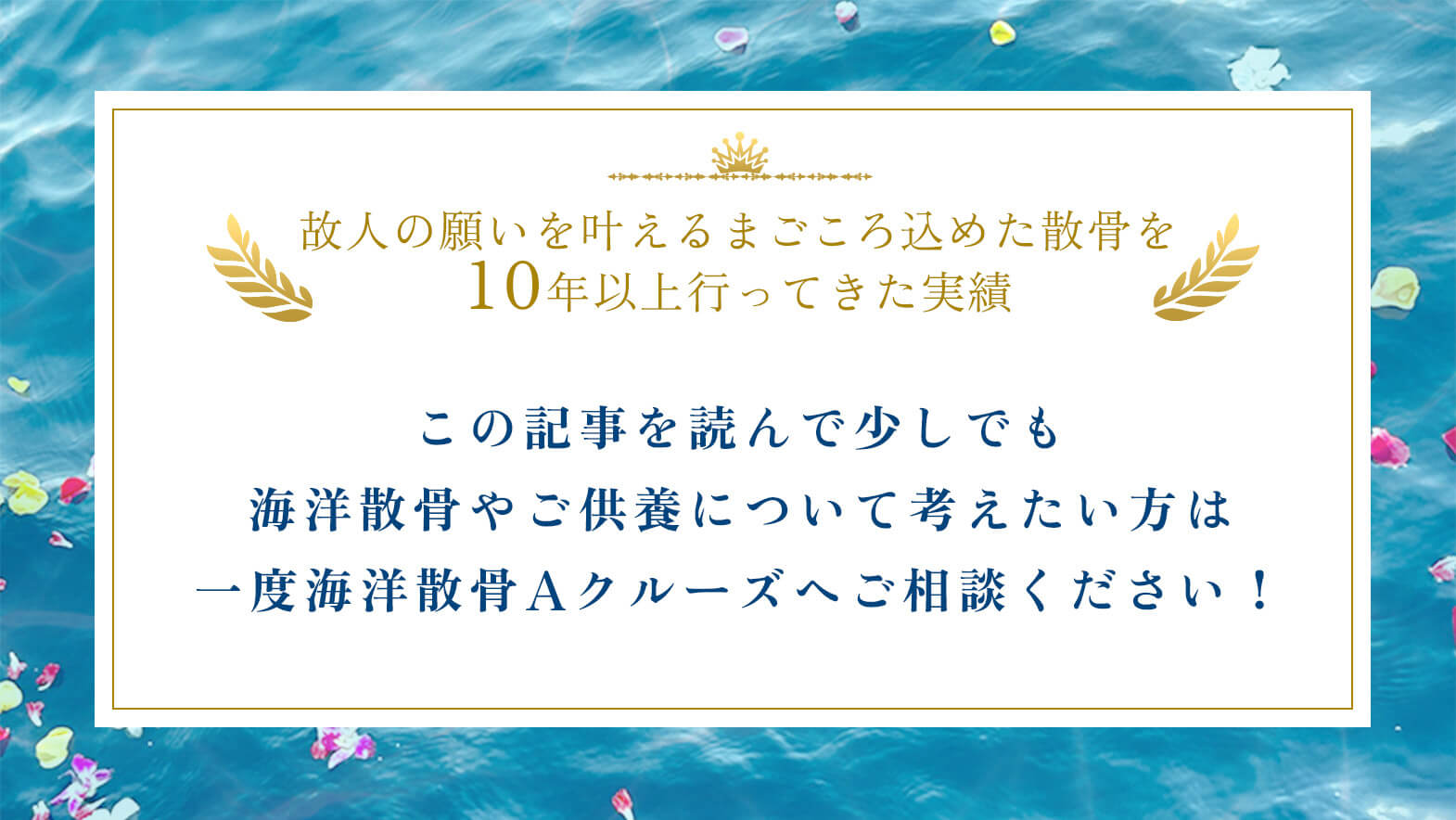近年では、生活環境の多様化や少子高齢化によりお墓や納骨堂にご遺骨を置かずに、自宅を供養の場とする方も多くなっています。
ここでは、自宅供養に関することや、ご遺骨を自宅供養する際のメリット・デメリット、そして自宅供養として選ばれる供養方法の種類などを解説します。
Contents
自宅供養とはどのような供養方法?
自宅供養とは、ご遺骨をお墓や納骨堂に安置するのではなく、自宅に持ち帰り供養をする方法のことを指します。
自宅供養は、大きな括りで手元供養と同じ意味として呼ばれたりしますが、厳密に言うと異なります。
自宅供養がご遺骨の全てを持ち帰り供養するのに対して、手元供養はご遺骨の一部を持ち帰り供養します。
どちらの供養方法も特定の規約や制約もないので、ご遺族は自由に供養方法を選択することができます。
自宅供養とお仏壇での供養は異なる供養方法である

自宅供養を行う際には、お仏壇がないと供養できないように思われますが、自宅供養はお仏壇を必要としない供養方法になります。
自宅供養は、故人のご遺骨を中心として故人の供養を行うのに対して、お仏壇は宗派のご本尊を中心としてご先祖と故人を含めた方々の供養を行います。
一般的に、お仏壇にご遺骨を安置することはあまりなく、通常は四十九日を過ぎるとお墓や納骨堂にご遺骨を納めます。
そして、日々の供養はお仏壇を通して行い、お盆や命日などにお墓に訪問して供養を行います。
自宅供養では、ご遺骨を自宅に安置するので日々の供養を含める全ての供養を自宅で行います。
そのため、自宅供養は毎日家にいながら常に故人の一番近い場所でお参りができる供養方法といえます。
そもそもご遺骨はお墓や納骨堂に納骨しなくても良いの?
従来のお墓などに納骨する供養方法では、故人を火葬した後にお墓や納骨堂にご遺骨を安置して供養してきました。
納骨して供養することで、残されたご遺族は故人の死を受け入れ心の整理を行ってきました。
一方で、自宅供養をする際には前述のようにお墓や納骨堂に納骨せずに自宅でご遺骨を保管します。
ご遺骨の取り扱いに関する誤り

自宅供養でのご遺骨の取り扱いに関して、誤った知識を持たれている方もいます。
ご遺骨の取り扱いに関して、詳しくみてみましょう。
ご遺骨は納骨しないと法律に違反する?
現在の日本国内の法律に関して、墓地・火葬・埋葬においては「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)」にて、墓地以外に納骨する行為は厳密に規定があり禁止されています。
しかし、納骨しないことに関しては前述の法律に記載されていません。
つまり、自宅などの屋内にご遺骨を保管することや、お墓などに納骨しなくても法律に違反とはなりません。
ご遺骨は納骨しないと成仏できない
ご遺骨は、納骨しなければ成仏ができないと考えられている方もいらっしゃるようですが、実際のところはそうではありません。
浄土真宗においては、納骨の有無に関わらず「即身成仏」という考えなので、亡くなった時に成仏するとされています。
また、仏教などでは亡くなってから四十九日で成仏して極楽浄土へいくとされているので、一般的にはそのタイミングで納骨を行いますが、納骨しないと成仏できないわけではありません。
ご遺骨を家に安置すると縁起が悪い
ご遺骨は、一般的に四十九日の法要を過ぎると納骨します。
そのため、その後も家に安置しておくことは縁起が悪いなどと言われることがあります。
実際の所では、宗教的な考え方でも特に縁起が悪いなどということはないので、問題ありません。
故人を強く思い出させるご遺骨を身近に置いておく事が、悲しみから抜け出せなくなるという考えや、故人にしがみついているなどと思わせるので、一部では縁起が悪いように言われることもあります。
どのような方が自宅供養を選択するの?

自宅供養を選択する方の背景には、人それぞれ経済的や社会的な要因が関係しています。
主な理由としては、以下のような事が考えられます。
墓じまい後の選択肢のひとつとして
墓じまいとは、現在管理しているお墓を撤去して、先祖や故人の遺骨を取り出し別の場所に移動させることを指します。
近年では、少子高齢化の影響でお墓を継ぐ方がいないなどの背景により、管理する事が困難になり墓じまいを選択する方も増えているようです。
墓じまい後は、永代供養や散骨などと共に自宅供養がひとつの選択肢となっています。
故人を亡くした悲しみを抱えたまま埋葬できない
大切な方を亡くしたばかりの時には、悲しみが深すぎてすぐに埋葬する気になれない場合もあります。
そのような場合には、心の整理がつくまで自宅にご遺骨を安置して供養をする選択肢もあります。
自宅供養には時間制限が無いので、ご自身の心の傷が時間とともに幾分か楽になるまでご遺骨を側に置いておくこともできます。
故人の意向を組んだ自由な供養を行いたい
生前に故人からご自身の供養方法を指定されていた場合や、遺書などにより従来の伝統的なお墓や供養方法にこだわらないで欲しいなどと指示があった場合にも選択されます。
型に組み込まれた堅苦しい供養ではなく、故人らしい供養がしたい方の選択肢としても利用されます。
自宅供養の方法として選ばれる供養の種類について

自宅供養には様々な方法がありますが、近年ではライフスタイルの変化や故郷などの住環境に合わせた供養方法なども多くなっているようです。
具体的な例としては、以下のようなものがあります。
骨壺のまま安置
お仏壇が家にある場合や、骨壺のまま供養したい方などは、自宅で保管できるスペースに安置します。
その際には、四十九日の法要にて使用した祭壇をそのまま利用する場合や、クローゼットなどに保管します。
ミニ骨壺に保管
骨壺の大きさは、一般的に10cm〜26cm程度のものがありますが、そのまま安置すると大きすぎる為に少し威圧感を受けることもあります。
また、目立つ場所に大きな骨壷を置いておく事をあまりよく思われない方もいます。
ミニ骨壺では、喉仏など限られたご遺骨のみ入れるので手のひらに乗る程度の小さいものがあります。
また、見た目にもインテリア性が高い骨壺もあるので、置き場所によって最適なものを選択すると良いでしょう。
収納可能な仏壇で保管
前述のように自宅で保管する供養では、人目につくことを嫌がられる方や、破損などの危険性を回避するために専用のお仏壇を購入することもあります。
仏壇によっては、骨壺を収納できるものもあるので、骨壺をそのまま安置する際の選択肢のひとつとなっています。
ミニ仏壇に保管
従来の仏壇は、和室というイメージが強いと思います。
生活環境の変化により、近年では洋室しかない住宅も増えています。
ミニ仏壇では、木製の他にもガラス製などモダンなタイプもあるので様々な場所でも違和感なく供養することができます。
アクセサリータイプ
アクセサリータイプは、遺骨やパウダー状にした遺灰を加工して、身に付けられるアクセサリーにして供養をする方法です。
シンプルな形状のものから、ネックレスやステンレス製のデザイン性にこだわったものまで様々な形状のものを作ることができます。
プレートタイプ
プレートタイプでは、ご遺骨をガラスや金属、石などに埋め込みプレート状にして飾り、リビングや寝室などに置いて供養を行います。
大型なものからコンパクトなものまで選べるので、置き場に困らずに作成することができます。
プレートには、生前故人が好きだった言葉や遺族からのメッセージなどを彫刻することなどできます。
花器や陶器などのインテリアタイプ
自宅供養では、花器や陶器などインテリア風に加工して供養する方法もあります。
また、ぬいぐるみの中にご遺骨を入れて身近な場所に安置して供養したりもします。
自宅供養のメリットとは

自宅供養のメリットは様々なものがありますが、ここでは代表する大きなメリットをご紹介します。
故人をより身近に感じることができる
故人とは心で繋がっているとはいえ、物理的に墓地や霊園で供養した際に故人を身近に感じることが難しいと感じる方もいます。
自宅供養では、物理的に近い場所にご骸骨があるので、毎日遠方までお参りする必要がないので日々身近に故人を感じることができます。
特にアクセサリーなどの持ち歩くことができる供養方法の場合には、場所を問わず身近に感じながら過ごすことができます。
墓石を建てて供養するよりも費用が抑えられる
日本最大級のお墓の情報サイトである「いいお墓」が、2024年1月に実施した「第15回 お墓の消費者全国実態調査(2024年)」の調査結果によると、購入した一般墓の平均金額は一般墓149.5万円とされています。
この金額の他にも、土地代や毎年の管理費用などがあるので経済的にも負担は大きなものになります。
自宅供養では、このような費用が発生しないので短期的はもちろん中長期的にも経済的な負担が少ないメリットがあると言えます。
お墓の管理が必要ない
お墓は、定期的に掃除や草刈りなどのメンテナンスをする必要があります。
日々のメンテナンスは、一般的に近隣の親族が行うことが多く、遠方に引っ越してしまった場合には管理が難しくなることもあります。
自宅供養の場合には、手元にご遺骨があるので管理など行う必要がありません。
また、子供や孫などにお墓の管理負担をさせたくないなど考えられている方にも、管理が不要な自宅供養はメリットと言えます。
宗教宗派など関係なく自由に供養できる
一般的にお墓には宗教や宗派などがあり、それにより作法などが異なります。
自宅供養には宗教などの制約がないので、故人を自由な方法で供養することができます。
お仏壇や祭壇なども必要ないので、省スペースな場所や空間を供養する場所とすることもできます。
また、寺院や霊園ではお供物など一定の配慮をする必要がありますが、自宅供養の場合は故人が好きだった食べ物を自由にお供えすることができます。
自宅供養のデメリット
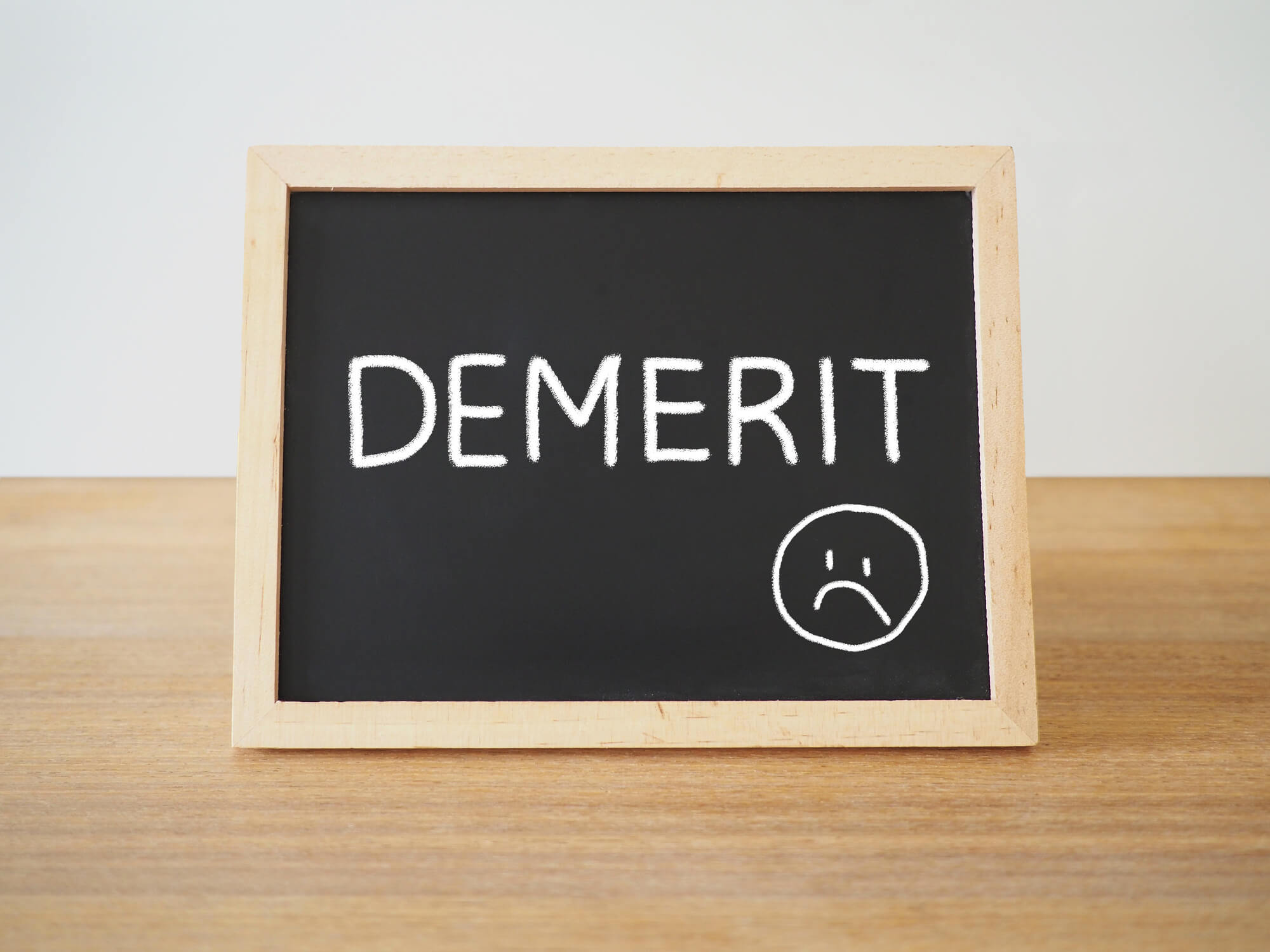
自宅供養には多くのメリットがありますが、事前に知っておきたいデメリットもあります。
親族からの同意を得られない場合がある
自宅供養は、以前に比べて認知度は上がってきているようですが、従来のお墓を建てる方法や納骨堂での供養が一般的なので、親族や家族の同意を得られないこともあります。
先祖代々のお墓を代々受け継ぐことを由とするご家族から、理解を得るのには時間を要する可能性があります。
気軽にお参りしにくい
近しい家族や親族は気軽に故人宅へのお参りができるかもしれませんが、会社の同僚や友人などご家族ではない方々は、自宅に気軽にお参りすることに抵抗がある場合があります。
そのため、少しずつ足が遠のいてしまうことがあるので、お付き合いを継続されたい方には「挨拶状で気軽にお尋ねください」などの手紙を送付すると良いでしょう。
ご遺骨の管理に責任が生じる
霊園や納骨堂などの場合には、適切な方法で管理されているので安心できますが、自宅供養の場合にはご自身で管理する必要があります。
特に自然災害などで被害を受けやすい地域に住んでいる方などは、被害を受けた際にご遺骨を取り戻すのは非常に困難となります。
ご遺骨や供養品を紛失する恐れがある
自宅供養では、前述のようにアクセサリーなどに加工して身につけることもあります。
手軽に身近な場所で供養をすることができる反面で、その手軽さ故に外出先などで紛失してしまうデメリットもあります。
普段からアクセサリーなど無くしやすい方は、特に注意して身につけるようにする必要があります。
自宅供養の注意点

自宅供養を選択する際には、気をつけておきたい注意点もあります。
独断で自宅供養を決めない
お墓の代表者がご自身の場合でも、自宅供養にするのか従来通りの供養方法にするのかなどは個人で決めるのではなく、ご家族や親族交えた上で了承後に取り進めましょう。
ご自身の考えと家族や親族との考えに差異があると、後々トラブルに発展する可能性もあります。
供養方法は、信仰や地域的な慣習などの要素も含まれる地域もあるので、十分に周りの意見を尊重した上で決めましょう。
将来的にお墓に納骨する可能性も考慮する
自宅供養を選択した場合においても、その後に気が変わりお墓や納骨堂に納骨することは可能です。
故人と離れ離れになりたくない意思が強いために自宅供養を選択したものの、時間の経過とともに気持ちの整理がついて、お墓に納骨したいと考えることもあります。
そのような場合には、火葬の際に取得した埋葬証明書がないと受け入れてもらえないので注意が必要です。
ご遺骨の保管には注意が必要
長期間に渡ってご遺骨を保管する際に、注意する必要があるのが湿気などによる「カビ」の問題です。
一般的に火葬の際は、800~1,200度の高温で焼かれるので、ご遺骨はほぼ無菌状態になります。
この状態でのカビの発生率はかなり低くなりますが、自宅で保管する場合には場所によって年中湿度が高くカビが発生する可能性があります。
ご遺骨を保管する際には、湿度と空調管理に留意して以下の場所に置くとよいでしょう。
直射日光が当たらない場所
自宅供養でご遺骨を保管する際に、避けて通るべき場所として直射日光が当たらない場所が挙げられます。
ご遺骨に直射日光が当たると、ご遺骨の温度が上昇して結露の原因になります。
そのため、窓際などの場所は避けた方が良いでしょう。
暗所で風通しのよい場所
直射日光を避けて押し入れの中や倉庫の奥などに安置するのも、あまりお勧めできるものではありません。
暗所なのはよいのですが、風通しが悪すぎると逆に湿度が溜まってしまいます。
定期的に換気をして空気の入れ替えをしている場所であればよいのですが、長期間締め切っている場所などは避けましょう。
1日を通して昼夜の気温差が少ない場所
ご遺骨の保管場所としては、1日を通して比較的気温の差が少ない場所が好まれます。
一時的に温度が上がる電化製品などの付近などもあまり好まれる場所ではありません。
特にご遺骨を置いてはいけないとされているのが、湿気が上がりやすい台所や湿気が溜まりやすい風呂場などの「水回り付近」です。
骨壺は完全に密閉されている訳ではないので、隙間から水分を含んだ外気が入り込みます。
短期間であればさほど問題はありませんが、長期的になると徐々に骨壺内が湿気ずいてしまい、最終的にはカビが繁殖してしまいます。
一度カビが発生すると取り除く事が困難で、臭いなどの問題にもなります。
残った遺骨の行き先と供養方法

自宅供養で保管する際に、前述のようにアクセサリーなど様々な方法で保管できるように加工した後の遺骨はどうするのでしょうか?
残った遺骨の管理方法は、今まで通り自宅で保管する方法と、別の方法で供養する方法の2つの方法があります。
手元に残ったご遺骨の供養方法は、以下のような方法があります。
永代供養
永代供養とは、寺院や霊園がご遺族や子孫に代わって永代にわたり故人のご遺骨の管理・供養を代行して行ってくれる埋葬方法のことを指します。
永代供養はお墓の継承などを必要としないので、従来は後継者のない方や身寄りのない方が選ばれてきました。
しかし、近年では「子供にお墓の管理負担をさせたくない」「お墓以外の供養方法を選択したい」などという考えの方にも選ばれています。
本山納骨
本山納骨とは、故人が生前信仰していた宗派の本山にご遺骨を納骨することを指します。
本来は開祖の下で供養を望む信者が対象でしたが、近年では信仰がなくても申し込みをすることで受け入れてくれるケースが多くなったようです。
散骨
散骨とは、ご遺骨を2mm以下のパウダー状にして散布する供養方法のことを指します。
散骨の種類としては、外洋に出て散骨を行う海洋散骨と、散骨専門業者が管理する山林に散骨をする山林散骨があります。
散骨は法律で禁止されている行為ではありませんが、いくつかのルールがあるので事前に確認して行う必要があります。
樹木葬
樹木葬は、散骨同様にご遺骨を自然に還す考えの供養方法ですが、墓石ではなくハナミズキや桜などの樹木をモニュメントとして植えます。
永代供養同様に継承者が不要な供養方法のひとつです。
前述でも少し触れましたが、ほとんどの山は国有林や私有地になります。
勝手に埋めて木を植えるなどすると、法律違反になるので注意が必要です。
まとめ
自宅供養に関してや、ご遺骨を自宅供養する際のメリットやデメリット、そして自宅供養として選ばれる供養方法の種類などを解説しました。
自宅供養は、従来からあるお墓や納骨堂での供養方法とは異なり、自宅でご遺骨を保管安置して供養を行います。
ご遺骨をプレートなどに作り替えて保管したり、アクセサリーやネックレスにして肌身離さず故人と近い距離で供養することもできます。
ご遺骨を自宅で保管する場合に、管理方法を間違えてしまうとカビを生えさせてしまい、供養としてあまり心地よいものでは無いこともあります。
手元に保管する以外のご遺骨は、散骨などを行い自然に還す方法もあるので、一度ご検討してみてはいかがでしょうか。